※これはエドウィン36〜38の続編です。先にそちらをお読み下さい。
●微えろネタあり。苦手な方は回れ右!●
「申し訳ございません。本日全て満室でして、ダブルが一部屋しかご用意できないのですが…」
───そう、形式的に答えるフロント係の言葉にオレは普段信じもしない神を呪った。
事の始まりは昨日の夕方。
国家錬金術師でなくなってからはリゼンブールの自宅を仕事の本拠地としているオレだが、
軍上層部からの直々の依頼や科学者としての研究絡みでセントラルや地方に出張する事も多い。
昨日も中央司令部へ急な呼出しが掛かった訳だが(大佐…じゃない将軍の野郎、また面倒な事を押し付けるつもりだな…)、
運悪くその電話を取ったのがたまたま焼きたてのパンを届けに来ていた幼馴染だった。
いつもなら電話を引き継いでそれで終わりなのだが、
オレのセントラル行きを知ったウィンリィは自分も一緒に行くと言い出したのだ。
なんでも、セントラルに本社のある機械鎧の有名メーカーによる新作発表会がちょうど明日から開催されるのだという。
ウィンリィ曰くアメストリスで機械鎧の聖地と言えばラッシュバレーであり、
実際腕に覚えのある技師が多く集まって切磋琢磨しているのもラッシュバレーだが、
最近は個人工房によるオーダーメイドだけではなく大企業による大量生産型セミオーダーもそれなりに需要があるらしい。
オレは運良く機械鎧整備師が身内だったからこの右腕も特別割引でオレ専用にフルオーダーできているが、
一般的にまだまだ高価な機械鎧が少しでも安い大量生産型に流れていくのも仕方ない事なのだろう。
目をキラキラさせてその会社の製品の特徴を力説するウィンリィの様子を見るに、
将来自分のライバルになるかもしれない企業の視察といった意味よりも、
単純に機械鎧の新技術や新素材を一刻も早くこの目で見たいといった意味合いが強いように思えた。
新作発表会は明日から1週間。入場チケットはラッシュバレーの仕事仲間から譲って貰ったらしい。
ここ1年程前からリゼンブールとラッシュバレーの仕事場を行ったり来たりする生活をしているウィンリィは
元々この新作発表会の開催期間中にセントラルに行ってその足でラッシュバレーの仕事場に戻るつもりで、
師匠のガーフィールさんにもそう話してあったという。
そして「どうせセントラルに行くのなら、一人よりも二人の方がいいもの。
長時間汽車に乗るのって暇過ぎて未だに慣れないのよね。エドが一緒で良かったー」
とニコニコしながら言うウィンリィに、オレが反対できる筈もなかったのだ。
それぞれ目的は違うものの、少なくともセントラルに着くまでは二人だけの旅行……
というのに一抹の不安があったのは否定しない。
……16年以上、ウィンリィとは幼馴染をやってきて。
長い長い旅と苦悩と葛藤を経て、1年ばかり前に漸く世間一般でいうコイビト同士というものにはなった。と思う。
時と場合にも寄るが、いいかげんキスくらいは動揺せずにできるようになった。
ぎゅ、と細い身体を抱き締めるのにもだいぶ慣れてきたと思う。
どっかの女たらしに知られたら鼻で笑われそうだが、それだけでもオレにしてみればかなりの進歩だろう。
だがそれでオレ達の何が変わったかというと、殆ど変わってはいないのだ。
互いの仕事が忙しくてイチャつく暇がないというのもあながち嘘ではないが、
この関係の維持を望んだのは他でもないオレだ。
───ウィンリィを全部手に入れる…そういう意味で「抱く」のは、オレが18…結婚できる年になってから。
これはオレの中での区切りと戒め。
12歳から軍の狗という身分と引き換えに研究費という名の桁違いの収入を得ていたオレだったが、
国家錬金術師でなくなったオレは今やウィンリィ以上に駆け出しの身であり、
修行中とはいえ機械鎧技師として立派に働く彼女に見合うだけの男になってからでないと彼女の全てを手に入れる資格はない。
他にも色々理由はあったりするのだが、とにかく大まかな部分はウィンリィにも説明して納得済みだ。
オレが18になって社会的にも責任の取れる身分になってから、改めて言うべき事は言うつもりでもある。
……自分で課しといて何だが、健康な若い男としてはこれはなかなかに厳しいものがあり、
天然無自覚ウィンリィのおかげで時々涙ぐましい忍耐を強いられたりもするのだが、それは今は関係ないので横に置いておく。
ともあれ、そんな微妙な関係の男女二人がリゼンブールからセントラルまでの小旅行。
最速の汽車を使っても丸1日掛かりの移動であり、その間はずっと顔を付き合わせる事になる。
幸い電話のあった翌日の早朝にセントラル行きの汽車が出ており、その切符を2枚確保する事はできた。
到着は当日の夜遅くになるので中央司令部に顔を出すのは翌日にするにしても、
当然セントラルのどこかのホテルに部屋をとる事になる。
緊張するなという方が無理な話だ。
つい、「せめてアルが一緒なら…」と今は遠い東のシン国で錬丹術の勉強をしている弟に救いを求めたくなってしまう。
尤も、アルに泣きついたところでニッコリスッパリ「いってらっしゃい」と送り出される可能性の方が高いか。
というかあいつなら絶対、心より状況を楽しんでオレとウィンリィを送り出すに決まっている。
オレとしてもウィンリィを後日一人でセントラルに行かせるくらいなら、自分が一緒の方がまだマシだった。
昔、無理を言ってリゼンブールからセントラルに出張整備に来て貰った事があるが、
現地で迎えがあるのとないのとでは大違いだ。
ウィンリィは「大丈夫よー」と気にもしないだろうが、国がひっくり返ってからまだ完全には安定していないこのご時世、
セントラルみたいな都会に若い女を一人で行かせるのには安全面で抵抗がある。
昼間はまだしも、汽車の到着が夜中になるなら尚更だ。
つまり最初からオレにウィンリィの提案を断る道などなかったと言える。
知らず大きな溜息をついたオレを、ウィンリィがきょとんとした目で見返した。
「どうしたのエド? なんだかもう疲れてるみたい」
「なんでもねぇ…」
「最近仕事場に篭りっ放しであまり運動してなかったでしょ。いやねぇ、もう更年期障害?」
「誰が更年期だ、オレはまだぴちぴちの17だっつーの!!」
汽車の向かいの席で「同い年なんだから知ってるわよ、冗談に決まってるじゃない」とけらけら笑うウィンリィ。
意図的に乗せられた訳ではあるまいが自分で今は17だと、宣言した18歳までは半年以上あると、
改めて念を押してしまった形になってしまいオレは内心項垂れた。
ほんと何をやっているんだオレは。
努めてなんでもないように、意識しないようにウィンリィと会話を交わすがきちんと受け答えできていたのか怪しい。
その一方、リゼンブールの旧友の事、ラッシュバレーの仕事仲間の事、シンからの手紙の事、
ここ暫く互いの仕事が忙しくてろくに話せなかった分を取り戻すように
ぽんぽん話題を振ってくるウィンリィはいつも以上にはしゃいでいるように見えた。
やがて外の景色にも飽きてきた頃、
決して座り心地がいいとは言えないボックス席でうとうとしだした彼女に自分の上着を掛けてやる。
これで暫くは静かになるだろう。
こうしているとアルと2人で旅をしていた頃を思い出す。
長距離を移動する事も多かったのでオレもよく汽車で寝入ってしまったものだが、
アルもこんな感じでオレを見守ってくれてたんだろうか。
汽車が出発してから既に半日以上が過ぎていた。
状況は刻々と進んでいる。
朝食と昼食はウィンリィが用意してくれた大量のサンドイッチとコーヒーで済ませた。
セントラルに到着する頃にはレストランも閉まっているだろうから夕食はどこかの停車駅で軽食でも買うつもりだ。
「…ん…」
微かに聞こえた寝言にそちらを見やれば、ウィンリィは上着に包まって完全に熟睡体制に入ったようだった。
出発時間から考えると、今朝は夜も明けないうちからオレの分までサンドウィッチを作ったのだから無理はないが。
(呑気なもんだよな…)
ウィンリィの長い睫の下に影が落ちている。
ふっくらしたピンク色の唇が半開きになっていて、妙に艶かしい。
上着が掛けられていても分かる豊かな胸のラインは、呼吸によって規則正しく上下していた。
思わずそれらから目を逸らしてしまった自分に苦笑する。
───こいつはこいつで、何も警戒した様子を見せないのがなんだか悔しい。
意識するのはいつもオレばかり。
自分から「これ以上やらない」と宣言しときながら勝手な言い分だというのは分かっている。
それでもこいつといると愛しい気持ちでいっぱいになるのだ。
キスしたくなる。抱き寄せたくなる。
大切だから、こいつを裏切りたくない。泣かせたくない。守ってやりたい。
離れていると逢いたくて堪らなくなるのに、近くにいればいるで落ち着かない。
頭の出来にはそれなりに自信と実績があったが、
こいつといると理論や計算式ではどうにもならない事があるのだと思い知らされる。
これが人を好きになるという事なのかもしれないと、暮れ行く窓の外を見ながらぼんやり思った。
「もう着いちゃったじゃないの! やっぱり起こしてくれたら良かったのに!」
「起きて早々しっかり弁当食ったんだからいいじゃねーか。まだ足りないのか? あんまり夜食うと太るぞ」
「お弁当選びたかったという意味じゃなくて! ああもういいわよ、勝手に寝こけちゃったあたしが悪いわよ!」
「なに不貞腐れてんだよ。ほら、行くぞ」
時刻は既に夜23時過ぎ。
セントラルに到着早々、やけに機嫌の悪いウィンリィを促して先を歩く。
実のところ、ウィンリィが後半寝てくれたおかげで必要以上に気を張らずに済んで助かった。
あれ以上二人で顔を付き合せていても、ろくな返事ができなかったに違いない。
後は無事ホテルに着けばこの「旅行」もオシマイ。
明日の朝からはそれぞれ別行動になる。
ウィンリィは久しぶりにグレイシアさんとエリシアちゃんにも挨拶したいと言っていたからセントラルにもう1泊くらいするかもしれないが、
オレはおそらく泊まるとしても軍内部か研究所で雑魚寝か、もしくは余所の地域に急行する事になるだろう。
辛うじて街頭に照らされた暗い道を並んで歩きながら、ウィンリィがきょろきょろと周囲を見渡した。
国一番の都会とはいえこの時間になると人も車もぐっと少なくなる。
出歩いているのは浮浪者か酔っ払いばかりだ。
ウィンリィを一人で放り出さなくて良かったと心から思う。
「…こっち? 前に泊まったホテルじゃないの?」
「ああ。駅からちょっと歩くが、オレがよく利用するホテルがある。
そこならこの時間でも空いてるだろ。朝食のクロワッサンが美味いんだ」
「へぇ。それは楽しみね」
心なしか、ウィンリィがホッとしたように微笑んだ気がした。
ウィンリィが言うホテルは随分前にアルも一緒に泊まった軍のホテルの事だろう。
あの時はヒューズ…さんの事とかスカーの事とか白黒ネコ探しとか、
とにかくバタバタしててゆっくりホテルの部屋で休むなんて事はできなかったが、
ホテルを変えるのは何も思い出が辛いだろうといったセンチメンタルな理由だけではない。
中央司令部は殆ど顔パスとはいえ、今のオレは正式には軍属ではないのだ。
極秘で依頼を受けてのセントラル滞在になる事もあるので、
こっちに来た時はなるべく軍絡みのホテルは使わないようにしていた。
加えて、今回に限れば女と二人だけで夜中に泊まったなんて事が
ホテルを通じて軍の奴らにバレたりしたら後で何を言われるか分かったものじゃない。
緊急の用事があった時の為に大体この辺りのホテルを使っているという事はマスタング組の連中は知っているが、
例えやましい事がなくても可能な限り危険は避けるに限る。
長年愛用している自分のトランクとウィンリィの工具箱(因みにウィンリィはこれとは別に大きな旅行鞄を肩に提げている。
リゼンブールとラッシュバレーの往復は大荷物になるので工具箱くらい置いておけばいいのに、愛用の道具は手放せないらしい)を
両手に提げて夜道を歩くこと10分ばかり、やがてこざっぱりとしたホテルが目の前に現れた。
築30年にはなるだろうホテルだが落ち着いた外装と部屋の掃除が行き届いてるせいかさほど古い印象はない。
専属のポーターがいない分宿泊料も庶民的なので、たまに長期間の滞在になる時は助かっていた。
ウィンリィを促して広くもない玄関ホールに入り、フロントに向かう。
シフトが違うのかそこに居たのが顔馴染みの若いフロント係ではなかったのに思わず安堵したオレは、予想以上に小心者らしい。
「すみません。───シングルを二部屋、お願いします」
カウンターで一気に吐き出して、心の中で息をついた。
これで何の問題もないはず。
後は互いに鍵を掛けて朝まで顔を会わせないようにすればいいだけだ。
ほんの僅かに間が空いたのは──意識の奥底でまだどこか迷っていたからかもしれない。
ウィンリィは、オレと二人だけでホテルに泊まるという事に何を思っていたのか。
もしここにアルが居れば、以前軍のホテルに泊まった時のようにオレとアルでツイン一部屋。ウィンリィがシングル一部屋。
最初から迷う事など何ひとつない部屋割りになっていただろう。
だが、今ここにアルは居ない。
そして昔と違い、今のオレとウィンリィは曲がりなりにもコイビト同士で。
順番は違うがプロポーズもどきもかましていて。既に1年そのつもりで付き合っていて。
──だけどまだ一線は越えてなくて。あと半年は越えないと、ウィンリィにも言ってあって。
だからリゼンブールで頻繁に互いの家を訪れても、どんなに遅くとも夕食後には必ず自分の家に帰っていた。
それが暗黙の了解だった。
──もし…もしここでオレが素知らぬ顔で二人一部屋を取れば、ウィンリィはどうしただろうか。
慌てて反論するか、それとも『オレを信じて』納得するのか。
怖いもの見たさで知りたかった気もするが、
万が一普通にスルーされたりしたらオレの身が持たないのも確実だった。
「少々お待ち下さい」
初老のフロント係が宿帳をぱらぱらと忙しく捲るのがやけに長く感じた。
自ら甲斐性なしを宣言したも同然のオーダーを告げた自覚があるせいか、
オレの一歩後ろに立つウィンリィを振り返る事ができない。
やがてフロント係がすまなそうに顔を上げた。
「申し訳ございません。本日全て満室でして、ダブルが一部屋しかご用意できないのですが…」
───こうして、長々と続いた前振りを経て冒頭に戻る。
「ちょっ……冗談だろ!? 今までこのホテルで部屋取れなかった事なんかないぜ!?」
フロント係の言葉に、我ながら情けないくらい動揺していたと思う。
「本当に申し訳ございません。こちらとしても、ご予約のお客様優先となりますので…」
「じゃ、じゃあ、そのダブル一部屋とシングル一部屋、でなきゃダブル二部屋でもいいから!」
「実は一部の部屋が改装中でして、今夜は他のダブルもツインも全て埋まってしまっているのです。
明日なら二部屋ご用意できるのですが…」
「……………」
迂闊だった。
何年も各地を旅していて、ホテルを事前予約した事など一度もなかったからすっかり失念していた。
冷静に考えれば、現地でいきなり部屋を一つ取るのと二つ取るのとでは勝手が違うのも当然だ。
オレ一人、もしくはアルと二人で一部屋だったらホテル側もまだ融通利かせ易いだろうが、
二部屋ではそうはいかないだろう。
がしがしと頭を掻くと、オレは漸くウィンリィを振り返った。
「…しゃーねぇ。ウィンリィ、おまえ一人でここに泊まれ」
「え?」
「他のホテルも空いてる保証はねぇ。オレは今から直接司令部に行く。運が良ければ仮眠室か…最悪、ソファでも使うさ」
「で、でもこんな時間だよ!? エド入れるの!?」
「知ってる奴が夜勤に出てくれてたらいいけどなぁ……まぁなんとかなるだろ」
「そんな適当な…大騒ぎになったらどうするのよ」
「それで将軍でも呼び出されたらオレの身分も証明されて楽なんだけどな」
「それはそれで怒られるでしょ!」
「事情を話してグレイシアさんとこに頼めば泊めてくれそうだけど、
小さい子供が寝ている家にこんな時間に押し掛ける訳にもいかねーだろ。
…ってそうだ、中尉…じゃないホークアイ大尉がいた!!」
「…リザ…さん?」
「ああ。大尉の家はすぐそこだ。そんなに大きくないアパートだけど、確かソファもあったしおまえ一人なら泊めてくれると思う。
もし夜勤で留守だったらオレが司令部に泊まり易くなるし、そしたらおまえがホテルに泊まればいい。おおナイスアイディア!」
持つべきものは頼りになる大尉と自分の記憶力。
あの人なら、オレ達の事を深く追求せずに色々察してくれるだろう。
ハヤテ号もウィンリィなら顔面に飛びついたりせず歓迎してくれるはずだ。
1億分の1くらいの確率で将軍が先客として大尉の部屋に居る可能性もないではないが……
これに関してはまだ当分有り得ないと、オレですら分かる。
毎度人の事をからかう前に自分の事をなんとかしろってんだあのクソ将軍。
「じゃ、とにかくその一部屋押さえといてくれ。どっちにせよ戻ってくるからさ」
「畏まりました」
「ウィンリィ行くぞ、大尉の家まで送ってくから───ぐへ!?」
フロントに告げ、踵を返して出口に向かおうとして。
いきなり襟首の後ろを引っ張られ、オレは思いっきりむせた。
すれ違いざまにウィンリィが手を伸ばしてオレのシャツの首を掴んだのだ。
「ごほげほごほっ……おま、何すん…!」
オレが動きを止めたのを確認してすぐに放してくれたものの、乱暴過ぎる。オレは猫の子じゃねぇぞ。
涙目で文句を言おうとしたオレを、ウィンリィがキッと見据えた。
そして今度は両腕でオレの右腕を抱きかかえるようにしがみ付く。
これが生身の腕の方だったらさぞ柔らかい感触を楽しめただろうに──ってそうじゃなくて!
「あたしは平気よ、ダブルで一緒の部屋でも。他を探す必要はないわ」
「ウィン、リィ!?」
今までで一番動揺するオレを余所に、ウィンリィはにっこりと笑って言葉を続けた。
「ね、『兄さん』。兄妹だもの、ダブル一部屋でも気にする事ないわ。あ、記帳しますね」
「……………………」
オレにしがみ付いたまま手を伸ばすと、
咄嗟に何も言えないオレに代わってカウンターの宿帳にすらすらと名前を書くウィンリィ。
躊躇いもなく書かれたエドワード・エルリックとウィンリィ・エルリックという文字がなんだか他人事のように見えた。
「有難うございました。523号室になります。こちらルームキーになりますので、お出掛けの際はフロントにお戻し下さい」
「有難う。さ、兄さん早く行きましょ。長旅で疲れちゃった」
よく見ればウィンリィの顔は笑っているのに、目は笑ってない。本気だこいつは。
こうなると何を言っても無駄だろう。
キーを受け取ったウィンリィがぐいぐい奥の階段へと引っ張るのに、オレは黙ってついて行くしかなかった。
同じ金髪とはいえ今までのやり取りからして絶対兄妹には見えなかっただろうに、
フロント係が何ひとつ驚いた様子を見せなかったのが唯一の救いかもしれない。
これが接客のプロって奴か。
「…ていうか、兄と妹でも普通ダブルはないだろ。どんなキョウダイだ」
「姉と弟の方が良かった? 2年前ならその方がしっくり来ただろうけどねー」
「昔の事は言うな、今はおまえより背高いんだから弟はないだろ!!」
「はいはい大きくなって良かったわねー兄さん」
「なんか納得いかねぇ…」
階段を黙々と上がりながら沈黙に耐えかねてぽつりと呟いたオレに、
腕から手を離したウィンリィがこちらを見ないまま平然と返す。
そりゃ17のガキ二人が夫婦だと言い張るよりは、キョウダイの方がまだ世間的に納得し易いだろうが…
そう考えて、改めて心臓がどきりと鳴った。
階段から部屋までの距離が馬鹿みたいに長く感じる。
夜中なので足音が響かないよう注意して薄暗い廊下を歩くが、オレの心臓の音がウィンリィに届くんじゃないかとさえ思った。
「523……あった、ここね」
小声で呟いたウィンリィがキーを使って部屋の鍵を開ける。
入り口のスイッチを押すと控えめなオレンジ色の照明が中を照らした。
「ほら、ぼーっと入り口に突っ立ってないで早く入って」
「あ、ああ…」
ウィンリィに促されるまま初めて見たダブルの部屋に足を踏み入れる。
後ろでウィンリィが扉の鍵をかけた音を敢えて無視しつつ、何気なく部屋を見渡した。
シングルの部屋と比べても内装自体は殆ど変らないようだ。
入り口付近の扉はユニットバスと洗面台とトイレに繋がっていて、
部屋の中央にベッドメイキングされた大きめのベッドがひとつ。
ランプの乗ったサイドテーブルがあって、その奥の窓際に簡素な丸いテーブルと椅子が2脚。
大きな鏡のついた化粧台兼机兼チェストがベッドの足元側の壁際にひとつ。
…最後の希望として微かに期待していたソファは存在しなかった。
「……………」
とりあえず荷物を床に降ろしたものの、何を言えばいいのか分からない。
ウィンリィの方を見れなくてなんとなく自分の靴先に目をやった。
(床……でも寝れない事はない、な)
今更フロントに頼んで予備の毛布を借りるのも変だし、部屋の隅で上着に包まれば一晩くらいはどうとでもなる。
春も終わりのこの季節、寒くて凍えるという事はない。
書斎で調べ物をしてて気付けば床に転がって朝を迎えていたなんて事は今も昔も珍しくはなかった。
……今回の場合、寝心地の前に眠れるかどうかの方が問題だが。
まぁ2、3日眠らずに研究する事もザラだったから、
一晩眠らなかったところで明日の仕事にそう大きな支障もないだろう。体力には自信がある。
本当ならウィンリィを残してオレだけ部屋を出た方がいい気がするが、
鍵を掛けたという事はウィンリィはそこまでする気はないという事か。
そもそも、夜中に部屋を出て廊下をウロウロしていたらホテルの方に不審者扱いされてしまうかもしれない。
「エド」
「はいぃ!?」
うわ。すっげぇカッコ悪い。
後ろから呼ばれた声に、思わず返事が上擦る。
動揺してるのがバレバレだ。
「もう遅いし、先にシャワー浴びてきていい?」
「あ…ああ」
「ありがと」
手早く荷物を整理したらしいウィンリィが、着替えを手にバスルームへ向かう。
ポニーテールが扉の向こうへ消えていくのを見送って、オレはベッドの端にどっかと腰を下ろした。
やがて部屋に響いてきた水音をかき消すように、大きな溜息を吐く。
───なぁ。おまえはどういうつもりなんだ?
一緒に旅行するという事を素直に喜んでいたウィンリィ。
折角の解決策を蹴ってフロントに嘘までついて、ダブルの部屋にオレと泊まる事を選んだのは何故だ?
18になるまでオレがおまえに手を出さないと信じているから?
夜中に部屋を探して街を駆けずり回らないで済むよう気を遣っただけ?
だけど、男には色々事情もあって。
惚れてる女を前にして、ふとした拍子で理性が飛ぶ事だって充分あり得るのだ。
一方通行の片思いならまだブレーキも掛けようがあるが、相手も自分を好いてくれてると知ってるなら尚更だ。
今までだってギリギリ踏み止まれたものの、危なかった事は何度もあった。
それは当事者のウィンリィもよく分かってるはずで。
どちらにとっても逃げ場のないホテルの部屋で、朝までオレの理性が持つという保障はなくて。
ウィンリィがシャワーを浴びる音が、なんだか意味深に思えて。
(………OKって事なの………か?)
人間という生き物は、高尚なフリして繁殖期のある家畜などよりずっと動物的で節操がない。
実際に子孫を残す目的の『本番』でなくても性的快楽を貪る事はできる。
やろうと思えば一人でも可能だし───二人でも可能だ。
『本番』抜きで、お互い気持ちよくなるのは『18までやらないルール』に対してセーフ、なのか?
(ってそこで妥協してどうすんだオレのアホ─────!!)
ずっと考えないようにしてた事が具体的に浮かんで、オレは頭を抱えて唸った。
ぶんぶんと壊れたオモチャのように首を振る。
そうじゃねぇ、オレが18までって決めたのはそういう事じゃねぇんだ!!
必死に元素記号を羅列して不埒な想像を追いやろうとするが、一度脳裏に浮かんだ光景はなかなか消えてくれない。
そりゃそれが可能ならこれは願ってもないチャンスと言えない事もないしいつも一人で処理してたのをウィンリィにやって貰えたら嬉しいし
あいつも気持ちよくしてやりたいし寧ろ女は本番が大変らしいから今のうちに慣らして───ってだから止めろオレ!!
第一、そんな据え膳状態で本当に最後までやらずに止まれる自信なんかこれっぽっちもねぇ!!
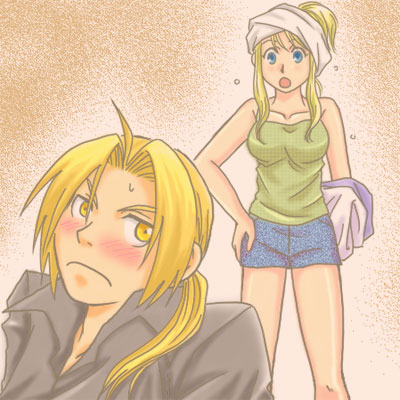
「………何やってんのあんた。お風呂空いたわよ?」
ベッドから転げ落ちて床をゴロゴロしていたオレに、頭上から呆れたような声が落ちる。
どうやらオレが悶々としていた間にそれなりの時間が過ぎたようだった。
湿った髪をタオルで頭上に纏めたウィンリィは寝巻き代わりと思われるキャミソールに短パン姿で、
ほんのりピンク色に火照った肢体はいかにも食べ頃な瑞々しさを溢れんばかりに主張している。
それを視界の端で確認しただけで、自分の顔がカーッと熱くなったのが分かった。
さっきからヤバかった下半身にダメ押しのように血液が集中する。
「じゃ、じゃあオレ入ってくるから!!」
───逃げるようにしてバスルームに飛び込んだオレは多分、色んな意味でギリギリだったに違いない。
兄さん……アンタ……(哀れみの目)(酷っ)
長いのでウィンリィ視点の後編へ続きます。
前編を表に置いてる時点でヤらないのは決定してるようなもんですが。(…)
(09.09.12.UP)