「……………………」
「……………………」
「……………………」
「……………………」
根無し草を自称する兄弟がリゼンブールに戻り、本当に久し振りに4人揃った食卓。
いつもだったら旅の間の出来事をアルが面白おかしく話してくれたり、
逆にあたしがリゼンブールであった事件を報告したりの楽しい夕餉になる筈だった。
なのに。
なんなのよ、目の前に座る馬鹿豆のどす黒いオーラは!!!
人が折角腕によりをかけて作ったディナーを黙々と口に運びながらも、不機嫌さを隠そうともしない。
あんまりそれが分かり易いものだから、
同じテーブルに座るアルもばっちゃんも怯えて……というより呆れて物が言えない状態だ。
ばん。
空気の重さに、とうとうあたしは切れた。
掌でテーブルを叩き、エドを睨みつける。
「……ちょっとエド。マズイならマズイって言えばいいでしょ!?」
言いながら、自分でも情けない理由だと思う。
これでも頑張ったつもりだったのだ。
珍しく機械鎧を壊さずにメンテナンスだけで帰ってきたエドへのささやかなご褒美のつもりで、こいつの好きなシチューを作った。
これだって、都会でいいもの食べる事だってあるだろうこいつの舌に対抗すべく密かに研究を重ねていたのだ。
だけど、結果は惨敗。
長い付き合いだ。直接言われなくたってエドの顔を見れば分かる。
勿論、ちゃんと味見はした。
ばっちゃんからも特にダメ出しはなかったし、あたしとしてはそんなに悪くない出来だと思う。
それでもエドワードさんのお口には合わなかったという事なのだろう。
「………そうは言ってねぇ」
「カオが言ってるわよ!!」
ああもう、しらじらしく目を逸らさないでよ!
いつもなら10分で平らげておかわりを要求するあんたが、未だに食べ終わってないのがいい証拠じゃないの!!
………あ。
やばい。
「もういい!! 悪かったわね、マズイもの出して!!!」
「ウィンリィ!?」
うっかり涙が零れそうになったのを席を立つ事で誤魔化し、リビングを飛び出す。
後ろでアルの慌てたような声が聞こえたけど、敢えてそれは無視させて貰った。
2階に駆け上がり、ベランダに出て扉を閉めたところでずるずると座り込む。
「……最低……」
そして押し寄せる自己嫌悪。
自分の料理の腕を棚に上げて、何やってんだろあたし。まるで子供だ。
田舎の澄んだ空気の中で星空を見上げながら、ぐしっと鼻をすする。
「大丈夫? ウィンリィ」
「…ってきゃあああ!!?」
突然、暗闇から現れた鎧に本気で心臓が止まるかと思った。
室内へと続く扉は今もあたしの背中に当たってる。
ここ以外、ベランダへ出る道はない筈なのに。
「あ、アル!? どこから……」
「あ、うん。外から階段錬成して登ってきたんだ。その方が早いと思って」
「そ、そう……」
………つくづく錬金術って反則だ。
驚いたせいで涙も引っ込んだ事に内心ホッとしつつ、
大きな身体を丸めて何でもないように隣にちょこんと座る幼馴染を見上げる。
アルって不思議。
こっちが意地を張るだけ無駄だと思わせる何かがあるから、逆らえない。
何より彼が隣にいるだけで安心する。
「ごめんねアル。折角帰ってきたのに気を使わせちゃって」
「ううん、ボクが好きで来たんだから。こっちこそ邪魔しちゃってごめんね?」
「あはは。それじゃお互い様ね」
「うん、そういう事」
ほんと、あたしは恵まれてる。こんなに優しい幼馴染がいて、他に何を望むのか。
───が。アルはそこで何か考えるように鎧の顔を傾けてみせた。
「…ね、ウィンリィ。ボクは食べれないし匂いも分からないから憶測なんだけど…今日のシチュー、いつもと作り方変えた?」
「う…うん。まぁ、そうかな。───失敗しちゃったけど」
家族だから。
普段は食事の時も何でもないように同じテーブルにつくけど、アル本人の口から食べれないという事実を聞くのは辛い。
彼にそれを言わせてしまった自分に嫌気が差す。
だけど当の本人は今はそんな事などどうでもいいとばかりに更に身を乗り出してきた。
「それでどんな風に作ったの?」
「どんな……って。料理雑誌、見たの。都会で流行ってるお店の秘伝のレシピとかって……」
「もしかして最近流行りのハーブたっぷり、スパイシーみたいな?」
「うん、そう。いっぱいスパイス入れて、普段あんまり使わない香草なんかも入れて……」
リゼンブールであれだけのスパイスを手に入れるのは結構骨だったけど、
いつエドが帰ってきても出せるように前々から準備してあったのだ。
都会に馴染んだエドは、昔ながらの田舎風シチューより最新流行のシチューの方が喜ぶと思って。
負けてなるものかって頑張って研究した。
───今思えば、なんであんなにムキになっていたのかも分からない。
「……それだ……」
「え? なに?」
額に手をやるアルの声が呆れてるような…苦笑するような微妙な色を含んでるように思えるのは気のせいか。
そして改めてあたしに顔を向けたアルは、人差し指を1本立てた。
「? アル?」
「ひとつ、秘密を教えてあげる。兄さんってね、旅先では全然注文しないんだよシチュー。
だけど一昨日、たまたま軍部の知り合いの人と町で出くわして、評判のレストランに一緒に入る事になったんだ。
そこの人気メニューがシチューでね。なし崩し的に兄さんもそれを食べる事になったんだけど……」
「…………………」
「……で。今、兄さんはここにいる」
がたん、と音がしそうな勢いであたしは座り込んでいたベランダの床から立ち上がった。
「兄さんなら台所にいると思うよ」
「有難う、アル!」
のほほんと手を振るアルを背後に残し、ベランダを飛び出てここに来た時と同じくらいの勢いでバタバタと階段を駆け下りる。
ばん、と台所の扉を開けると案の定そこにはシチュー鍋からおかわりをよそってるエドがいて。
ばっちり、視線が合った。
「………何やってんのよ」
「………うっせ。まだ食い足りねぇんだよ。なんたって育ち盛りだからな」
「豆のくせに」
「誰がミジンコ豆かぁ!!!」
言いながら山盛りになったシチュー皿をキッチンテーブルに置き、椅子に座ってそのままそこで食べ始めるエド。
むすっとした表情は先刻と変わらないけど。
それでもちゃんと、「あたしの作ったシチュー」だから食べてくれる。
それが子供っぽくて我侭なエドの─────最大級の優しさ。
なんだか、おかしさが込み上げてくる。
勘違いしていた自分にも。
不器用なエドにも。
「……ね、エド」
「ああ?」
「明日の夕食もシチューだから」
「はぁ!?」
「今度はばっちゃん直伝のロックベル家特製シチューだから安心して」
「…………アルの野郎、覚えてろ…………!」
今度こそ顔を真っ赤にして項垂れるエドに、あたしは声をあげて笑った。
「おまっ…、何笑ってんだよ!!」
「べっつにー。愛されてたんだなぁ、って」
「あ、あい……!?? なななななに言って」
「愛される家庭の味って大切よねー。あたしもまだまだ修行が足りないわ」
「………あじ………」
「他に何かある?」
「知るかっ!!!!」
完全にそっぽを向いてしまったエドの為にグラスの水を注ぎつつ、なおも笑い続ける。
本当に、お子様で。デリカシーなくて。
アルとどっちがお兄さんか分からないような事もしょっちゅうだけど。
それがエドだから。
───今は、これで充分。
たかが、シチュー。
されど、シチュー。
それは単に故郷の味って事なのかもしれないけど。
深い意味なんてないのかもしれないけど。
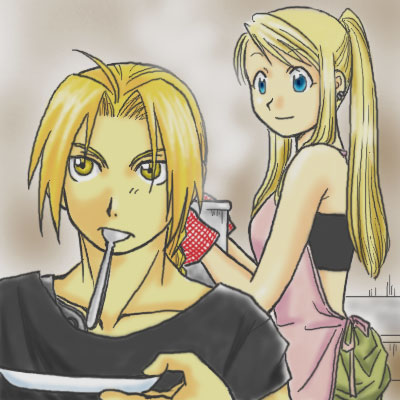
ねぇ。私は貴方の帰る場所になってるんだと、自惚れてもいいですか?
うっわぁ。
ものごっつ久しぶりにエロもラヴもない思春期を書(描)いたような…。
つーかコレ、エドウィンと言うより単なる幼馴染話……寧ろアルウィン……?
シチューネタは今更な気もしますが、やっぱり基本としてやっときたかったのですよ。
エドにとってシチュー=故郷の味なんだと思われ。
実際奴は都会の味に馴染むどころか、3度3度まともな食事をしているかも怪しいけどねー。
研究に没頭してたら平気で抜きそうだしなぁ。
嫌いな物も絶対食べない。そしてアルに怒られる、と。
あ、でも原作では意外にちゃんとしたもん食べてる事も多い…1巻の露店とか軍ホテルとか。
……まー深く考えてたら二次創作はできないんで!(逃げた)
(06.04.19.UP)